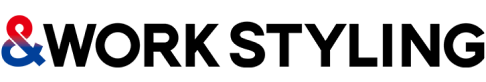導入事例
“週1日”から“週3日以上”へ
エンジニアの出社率が大幅に向上
リアルな会話が生まれ、より強まったチームの結束力
- 1-49名
- 情報サービス業・インターネット附随サービス業
- 専有スペースプラン(FLEX)
- 拡張性・柔軟性
- オフィス規模拡大
- オープンスペース利用
- 働き方改革
- 出張・外出先利用
- 高セキュリティ環境

本田忍様(左)と平野美由紀様(右)
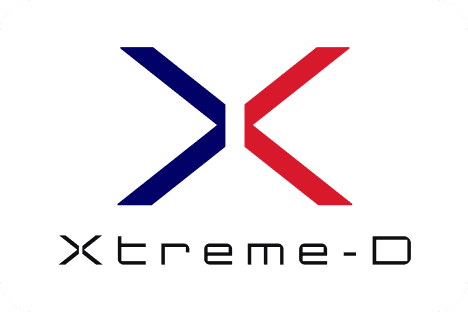
企業名
業種
高速クラウドサービスを開発・提供
従業員数
約10名
設立年
2015年2月
導入サービス
専有スペースプラン(FLEX)2024年10月~
取材対象者
業務執行役員 経営管理本部長 平野美由紀様/営業・マーケティング部 本田忍様
企業紹介
エクストリームーD株式会社様は、2015年設立のスタートアップです。AIを活用したデータ分析や創薬、流体解析といった先端分野では、高性能GPUやスーパーコンピューターといった膨大な計算リソースが欠かせません。同社はこうした計算リソースを必要なときに必要なだけ利用できるサービスを提供。GPU不足が深刻化するなか、 “AI時代のGPU難民を救う”を合言葉に、企業や研究者の開発・研究を支えています。
かつてはリモートワークが主流だった同社ですが、コロナ禍を経て、「仕事でも自分たちの“居場所”がほしい」という声が社内で上がり、改めてオフィスの必要性を見直すことに。ワークスタイリング 品川で「専有スペースプラン(FLEX)」の利用を始めたところ、社員の出社率が上がり、より良いチームビルディングにつながっているといいます。
導入の経緯やその後の変化について、業務執行役員で経営管理本部長の平野美由紀様、営業・マーケティング部の本田忍様にお話を伺いました。
■導入に至った経緯・背景
コロナ禍を経て、再び求めた“自分たちの居場所”
――ワークスタイリング導入の経緯を教えてください。
平野様:以前は品川区内の別の施設に入居し、最大20人が利用できる部屋を借りていました。エンジニアはリモートでも働けたものの、バックオフィスの担当者は全員出社していました。ところがコロナ禍で出社できなくなり、「この広さのオフィスを維持する必要性はあるのか」と問い直す状況になりました。
ただ、書類の保管場所は必要ですし、情報セキュリティの観点からも個室の確保は欠かせませんでした。そこで、3人ほどが入れる小さなオフィスへ移り、メンバーは基本的にリモートワークを続けていました。
そして新型コロナがようやく落ち着き、「よし、改めて動き出そう」というタイミングになると、やはり「自分たちの居場所が欲しい」という声が社内から出始めたんです。そこから、新しいオフィス探しが始まりました。
実は私自身、別の会社で働いていたときに、三井不動産の方とやりとりする機会が多かったんです。当時のご担当者がワークスタイリングの担当部署へ移られたことを記憶していて。そこでワークスタイリングの窓口に相談したところ、ちょうど品川の部屋が空いていることがわかり、内覧してほぼ即決しました。

■導入の決め手・プロセス
セキュリティ基準を満たす専有個室と、開放感のある共用エリア
――ワークスタイリングを選ばれた決め手を教えてください。
平野様:専有スペースを持ちつつ、オープンエリアや会議室も利用できる「専有スペースプラン(FLEX)」を契約しました。決め手の一つは、質の高いセキュリティが担保されている点です。
当社はISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)という第三者機関の認証を取得しています。認証を維持するには毎年の審査をクリアする必要があり、信頼獲得のため、あえて審査が厳しい認証機関に依頼していることもあり、物理的に区切られた個室の確保は必須です。審査では、防犯カメラの設置場所や録画データの保存期間、入退室管理の仕組みなど、かなり細かくチェックされます。ワークスタイリングは、こうした基準をしっかりと満たしており、安心感がありました。
もう一つのポイントは、開放感あるオープンエリアがあることでした。エンジニアたちは集中したいときに、あえて開けた場所で作業をすることが少なくありません。ですから、個室“プラスアルファ”の部分が私たちにとっては重要なんですね。見学した他社の物件も個室のセキュリティ面は問題なかったのですが、十分な広さのオープンエリアがありませんでした。
――ワークスタイリングを選ばれた決め手を教えてください。
平野様:はい。ワークスタイリングの担当者のレスポンスが、とにかく早かった! まさにこのスピード感は、私たち自身がお客さまとやりとりをする上で大切にしていることなんです。待たせる方よりも、待たされる方が時間を長く感じるものですよね。物件の選定は代表取締役の柴田と私の2人で進めていたのですが、「新しいオフィスに移りたい」というこちらの熱が高いうちにポンポンとやりとりが進みました。すぐに内覧日が決まり、契約まであっという間でした。

■導入による成果・効果
「自分たちの居場所」ができ、出社率が向上
――ワークスタイリング導入後、一番の変化は何ですか?
平野様:出社率が確実に伸びています。特に専有スペースを5席から8席へ、そして現在16席に広げてからは、目に見えて伸びていますね。
当社はリモートワークを推奨も制限もしていませんが、コロナ禍を経てリモートが主体になりつつありました。特にエンジニアは、週1回の定例会議のために出社する程度でした。それが今では、少なくとも週3日は出社するようになり、毎日来る社員もいます。やはり「自分たちの居場所がある」ということは、とても大きな意味を持つと実感しています。
――みなさんの満足度はいかがでしょうか。
平野様:定量的なアンケートはとっていませんが、日々のやりとりを通じた私の肌感覚では、メンバーたちの満足度は確実に上がっていると感じます。快適でなければ、オフィスに出てこないと思うんです。出社率の向上が、満足度の高さを証明しているのではないでしょうか。
本田様:当社は社員の約半数が外国籍で、みんな物事をはっきり言うタイプです。なので、本当に不満があれば、誰もオフィスに来ないと思います(笑)。

空間の共有が、チーム内の相互理解を後押し
――出社率が高まったことによるプラスの影響はありますか?
平野様:メンバー同士の会話が格段に増えて、どんどん良いチームになってきていると感じています。これは目に見えてはっきりとわかる変化ですね。
リモートでも、チャットツールでコミュニケーションを密にとっており、良い関係ではありました。それでも、同じ空間にいるからこそ生まれる何気ない会話には、かなり大きな意味があると思います。
本田様:私はバックオフィスの担当で、以前はエンジニアのチームと接する機会が多くありませんでした。でも、オフィスが広くなってからは、担当の垣根を越えて同じ部屋で過ごす時間が増え、自然とコミュニケーションが取れるようになりました。
エンジニアたちは英語でやりとりしているのですが、私は英語がそこまで得意ではありません。それでも対面だと、身振り手振りや表情で伝えられることがあるんですね。チャットツールだと、そうはいきません。
平野様:ちょっとした疑問も、お互いがその場にいるから気軽に聞ける。それがきっかけで会話が広がり、関係がより深まる。そうした積み重ねが、チームの雰囲気をさらに良くしてくれていると思います。
本田様:何より、エンジニアたちへの見方が変わりました。「この人、こんなに日本語話せたんだ」とか、「堅そうに見えたけど、実はよく笑う人なんだな」とか。エンジニアという職業柄、無口でまじめな人が多いイメージがあったのですが、こちらが言った冗談にちゃんと乗っかってくれたりして。そんな意外な一面を知ることで、自分自身がホッとした気持ちになれて、以前よりも自分を表現できるようになりました。
平野様:部屋に5~6人いると、自分が直接会話に加わっていなくても、その場の雰囲気から感じ取れることがあるんですよね。例えば「今、メンバー同士で心地よく会話ができているな」とか。こうした感覚は、その場にいる全員に安心感を与えてくれるし、お互いの人間味の部分をより感じられるようになる。結果として、居心地の良い空間が自然とできているのだと思います。

――オフィスにおける日々のコミュニケーションが、チームづくりにも良い影響を与えているのですね。
平野様:そうですね。エンジニアたちは代表の柴田が言葉で伝えたことを、チームで形にしていきます。そのためには、やはりコミュニケーションや信頼関係が何より重要です。
本田様:私は技術的なことまでは分かりませんが、エンジニアたちが真剣な表情で議論する姿を近くで見ることで、大変な仕事なのだと改めて感じています。その分、バックオフィスとして「彼らが働きやすい環境を整えたい」という思いが強くなりました。
平野様:そうですね。エンジニアたちはこれは逆の視点からも言えることで、リモート中心だと、エンジニアたちもバックオフィスの仕事が見えにくかったと思います。でも今は、自分たちがオフィスで快適に過ごせているのは、バックオフィスが陰ながら環境を整えてくれているからだ、ということを自然と理解してくれているのではと思っています。代表の柴田が言葉で伝えたことを、チームで形にしていきます。そのためには、やはりコミュニケーションや信頼関係が何より重要です。
――まさに、相互理解が深まっているのですね。
平野様:はい。だからこそ、オフィスという“場”を持つことが、互いの存在価値を認め合う関係性につながっているのだと思います。

オフィスの拡張で広がった働き方の自由度
――専有スペースは当初の5席から8席の部屋、そして16席の部屋へと段階的に拡張されました。当初から拡張は想定されていたのでしょうか?
平野様:はい。事業を加速させていくためには、メンバーも増やす必要がありますし、その際には当然、部屋を広げることも視野に入れていました。5席だった頃は、エンジニアたちは出社してもオフィスに荷物を置いて、すぐオープンエリアに出て行く、という働き方だったんです。でも、部屋が広くなってからは、みんな専有スペースに残って仕事をする時間が増えましたね。
本田様:エンジニアたちは集中の度合いや業務内容に応じて、オープンエリアと部屋を行き来しています。例えば、集中したいときや、外部とのやりとりが多いときは部屋で作業し、ちょっと気分を変えたいときに、オープンエリアに移る。そうやって、自分で働き方にメリハリをつけられるのはとても便利だし、仕事の効率も良くなります。
平野様:いつでも戻れる場所があるので、働き方の自由度がより高まった感じですね。
■効果的な活用シーン
全国の拠点を利用 出張先でも“いつも通り”働ける安心感
――専有スペースのほかに、ワークスタイリングをどのように活用されていますか?
平野様:全国に拠点があるのも、ワークスタイリングの魅力ですね。私たちは最近、京都にも新たな拠点を構え、大阪のデータセンターも利用しています。代表や私は出張が多いため、大阪や京都、さらには博多や名古屋など、各地のワークスタイリングをよく利用しています。
お客さまの機密情報を取り扱うことが多い関係上、出張先でもカフェなどではお客さまの情報が出るようなオンライン会議や集中した作業はできません。その点、ワークスタイリングなら全国どこの拠点でも万全なセキュリティの中で作業やオンライン会議ができますし、会議室を予約して、現地のお客さまをお迎えして商談することも可能です。すべての拠点が駅から徒歩5分圏内にあり、アクセスが良い点でも非常に助かっています。
地方にもドロップインできるワーキングスペースはありますが、普段使っているワークスタイリングの拠点というだけで安心感があります。ゆとりあるスペースで清潔感もあり、快適に仕事に取り組むことができます。ですから、出張が決まったら、まずは現地にワークスタイリングがないか、チェックしています(笑)。先日は博多のワークスタイリングに立ち寄ったのですが、居心地が良すぎて時間を忘れてしまったほどです。
本田様:私は展示会などイベント参加時に豊洲のワークスタイリングを利用しています。特にありがたいのは、時間を柔軟に使える点です。例えば「もう少し会場にいたいけど、オフィスに戻って仕事をするには今出ないといけない・・・」という時でも、すぐ近くのワークスタイリングで仕事ができる。だから、移動時間を気にせず、展示会をじっくり見て回れます。

――オープンエリアのカフェスペースも上手に活用されていると伺いました。
平野様:無料のドリンクやお菓子が充実していて、みんなよく出入りしています(笑)。代表や私は出張が多い分、出社しているときこそ、メンバーと短時間でもしっかり話すことを意識しています。「ちょっとお茶飲みに行かない」と気軽に声をかけやすいので、カフェスペースがコミュニケーションのきっかけになってくれています。
本田様:お菓子一つとっても面白くて。シナモン味のクッキーばかり食べるメンバーもいて、その人らしさが見えてくるんですよね。そういうちょっとしたやりとりが、職場の雰囲気をより和らげてくれている気がします。