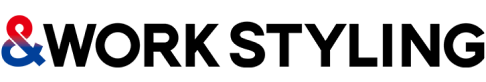導入事例
営業も採用も強くなる 老舗企業が“くすりの町”日本橋で広げる自由な働き方
- 100-499名
- 繊維・科学・石油・ガラス・ゴム・紙・セラミック・鉄鋼・金属
- 従量課金プラン(SHARE)
- 専有スペースプラン(FLEX)
- 支社・支店
- 働き方改革
- ハイブリッドワーク
- 出張・外出先利用
- 会議室不足解消
- すき間時間の有効活用
- 採用強化
- 充実した設備・心地よい空間
- 高セキュリティ環境
- 拡張性・柔軟性

和田清之様(左)と大久保幸則様(右)

企業名
業種
電子工業用薬品、試薬化成品
従業員数
320名(2024年12月末現在)
設立年
1904年
導入サービスと利用期間
「従量課金プラン(SHARE)」2024年6月~、
「専有スペースプラン(FLEX)」2025年8月~
取材対象者
代表取締役社長 和田清之様/常務取締役・試薬化成品部長 大久保幸則様
企業紹介
1904(明治37)年に大阪で薬問屋として創業した林純薬工業株式会社様。1950年に試薬製造を始めて以降、半導体や家電製品向け電子工業用薬品の開発にも注力し、着実に事業を拡大してきました。
東京営業所の会議室不足を解消し、柔軟な働き方を広げるため、2024年にワークスタイリングの「従量課金プラン(SHARE)」を導入。さらに2025年8月からは、日本橋三井タワーで専有スペースを持てる「専有スペースプラン(FLEX)」を契約されました。今後は新卒採用にも注力する方針で、ワークスタイリングの活用を通じて働き方の自由度を高め、採用力の強化につなげたいと考えています。
導入の背景や活用方法、そして今後の展望について、代表取締役社長の和田清之様、常務取締役・試薬化成品部長の大久保幸則様にお話をうかがいました。
■導入の背景と検討・意志決定プロセス
決め手は“体験済みの安心感”
——ワークスタイリング導入の経緯を教えてください。
和田様様:神田にある東京営業所が手狭になってきたことが、大きな理由です。会議室が一つしかないため、会議や1on1、評価面談などが重なるとかなり不便でした。とはいえ、オフィスごと移転するのは大変です。そこで、会議室を柔軟に使えるシェアオフィスの導入を考えました。
大久保様:実は以前勤めていた会社がワークスタイリングを契約しており、私自身もよく利用していたんです。清潔感があって、セキュリティ面や通信環境も安心できる。ですから、シェアオフィスを探すことになったとき、真っ先にワークスタイリングを社長に提案しました。ワークスタイリング神田が営業所から徒歩6~7分の場所にあることも大きかったですね。
和田様:私は1度、大手町のワークスタイリングをゲストとして利用したことがありまして。そのときの印象がとても良かったんです。「東京にはこんなシェアオフィスがあるのか」と感動したのを覚えています。大手町という一等地にあり、開放感があって内装もかっこいい。ですから、大久保から提案があったときは、ほぼ即決でした。

■導入プロセス
検討から1ヵ月足らずで導入
——まずは全拠点が従量課金で使える「Aプラン(SHARE)」を契約いただきました。検討から導入までの期間はどれくらいでしたか?
大久保様:1ヵ月もかかりませんでした。ワークスタイリングの営業担当者とはメール中心のやり取りでしたが、レスポンスが早いので非常にスムーズ。ノンストップ、ノンストレスで手続きが進んだので、相談から契約まであっという間でしたね。
■活用シーン
ワークスタイリングで会議室不足を補完
——御社の働き方について教えてください。
和田様:工場の社員を除き、多くが出社とリモートを組み合わせたハイブリッド勤務です。
大久保様:当社もコロナ禍を機にリモートワークが定着しました。2025年春からは、職種や役割に応じて働き方を選べるルールを導入しています。所属長の許可のもと、「フルリモート」「週2~3日出社」「完全出社」の3パターンから選びます。
例えば、試薬ビジネスの部門では約6割が週2~3日出社を選択しています。一方で、受注業務やお客さま対応の部署は完全出社が多いですね。現在、フルリモートの社員はほとんどいません。

——ワークスタイリングはどのように活用されていますか?
大久保様:神田の東京営業所には会議室が一つしかないため、会議や面談が重なるときはワークスタイリング神田の会議室をよく使っています。ウェブ会議や顧客向けの資料作成には、1人用の個室を使う社員も多いですね。
また、当社はセキュリティの観点から、カフェのような不特定多数が出入りする場所での業務は禁止しています。そのため、会社や自宅以外で働く際は、自ずとワークスタイリングを利用することになります。2024年6月から導入した「従量課金プラン(SHARE)」は全国の拠点が使えるため、移動の合間や出張時の利用も増えています。特に東京勤務の社員は働き方の自由度が高まり、若手を中心にモチベーション向上につながっていると感じます。
——ワークスタイリングの利用について何かルールは設けられていますか?
大久保様:なるべく多くの社員に使ってもらいたいという考えから、今のところ時間や回数に制限は設けていません。部署にかかわらず、希望する社員は誰でも自由に使えるようにしています。
■導入による成果・効果
東京の営業件数が昨年比158%まで伸長
——ワークスタイリング導入の効果があれば、ぜひ教えてください。
大久保様:営業担当1人あたりの訪問件数が明らかに増えています。直近のデータを昨年平均と比べると、全社で36%の増加。東京に限れば58%も伸びました。ワークスタイリング導入が、その大きな要因の一つだと考えています。全国に拠点があるため、営業担当が移動の合間に作業できる場所を確保できるほか、お客さまのオフィスの近くにあるワークスタイリングで商談ができるようになったことも大きいようです。
このほかにも、社員との1on1がしやすくなったこと、プレゼン資料の作成が効率的になったことなど、現場からは前向きな声が多く上がっています。

ワークスタイリング導入を新卒採用の力に
——採用にも力をいれておられますが、ワークスタイリング導入の効果はありますか。
大久保様:大きなメリットがあると感じています。清潔感のある空間に加え、セキュリティ対策も万全。さらに無料で使えるカフェスペースなど、働く環境としての魅力が高く、リクルーティングにおけるアピールポイントになっています。
和田様:社員数は2024年末現在で320人。1年間で23人増やすことができました。現在は中途採用が中心ですが、今後は新卒採用に軸足を置いていきます。2026年卒は10人ほど採用できそうで、将来的には20人規模に拡大していきたいと考えています。
柔軟な働き方は学生にとって非常に関心の高いテーマだと感じます。採用面接や会社説明会では、リモートワークの実施率について必ずと言っていいほど質問が出ます。一方で、学生たちは社内で交流を深めて仲間意識を高めたいし、チームプレーもしていきたい。そして、働きがいも感じたい。
学生の数は減り続け、採用はますます難しくなっています。だからこそ、企業としての魅力や価値観をきちんと伝えるブランディングが重要です。ワークスタイリングも活用しながら、学生の多様なニーズに応えられる環境をこれからも整えていきたいと考えています。

■今後の展望
営業拠点をワークスタイリングに移転
——2025年8月から、「ワークスタイリング日本橋三井タワー」で「専有スペースプラン(FLEX)」を契約いただいています。
和田様:東京営業所を、神田のオフィスからワークスタイリング日本橋三井タワーの専有スペースに移します。
東京勤務の従業員は約20人ですが、その多くが営業職で、オフィスにいる時間は限られています。そのため、全員分の固定席は必要ありません。専有スペースは、事務職の人数に合わせて7席分を契約しました。事務職もハイブリッドで働いているので、空いた席は営業職が使えますし、仮に席が埋まっていても、ワークスタイリングのオープンスペースを利用できます。
このように、従業員数や出社頻度の変動を吸収してくれる点がワークスタイリングの大きな魅力です。オフィスのキャパシティに縛られず、今後の採用にも積極的に取り組めます。今後は採用面接もワークスタイリングで行います。内装の美しさや快適さ、立地の良さは学生への大きなアピールになると思っています。
――移転は大変ではありませんか?
和田様:もちろん、さまざまな準備やお客さまへのご案内などは必要です。一方で、書類や備品を整理するよい機会にもなると感じています。
何を持っていき、何を減らすか。まさに東京のメンバーたちが議論してくれていますが、かなりの書類をペーパーレス化できそうです。これを機に、当たり前だった業務プロセスを見直し、効率化やDXを進められるかもしれません。

「くすりの町」日本橋への想い
——日本橋といえば「くすりの町」でもありますね。
和田様:当社の発祥は大阪市中央区の道修(どしょう)町(まち)です。製薬店や薬卸問屋が集まり、日本有数の「くすりの町」として知られています。私たちはこのルーツを大切にしており、採用ページでもしっかりと打ち出しています。
東京で「くすりの町」といえば日本橋。今も多くの製薬会社が本社を置いていますよね。やはり私たちも日本橋にオフィスを構えることで、薬業の企業であるという印象をより強く持っていただけるのではないかと思っています。
――レンタルオフィスではなく、通常のオフィスを借りることも検討されましたか?
和田様:実際、日本橋のビルに入居することを考えた時期もありました。ちょうどコロナ禍で、一斉に在宅勤務が始まり、将来のオフィス像を模索していました。私自身、当時はオフィスを借りて人数分の机を並べるのがスタンダードだと思っていたのですが、日本橋の中心部は賃料が非常に高い。ですから、もし借りるなら日本橋から少し外れたエリアで探すのが現実的だな、と思い巡らしていたんです。
しかし、コロナ禍を経てリモートワークが定着し、社内制度を整えていく中で、レンタルオフィスという選択肢ができました。ワークスタイリング日本橋三井タワーは、まさに日本橋のど真ん中にある。絶好の立地にありながら、初期費用を抑えられ、オフィスの維持管理の手間も不要。さらに、人数の変動に柔軟に対応でき、全国の拠点も使える。私たちのニーズに綺麗に当てはまったのが、ワークスタイリングだったんです。
——ワークスタイリングの活用について、今後の展望をぜひ教えてください。
和田様:もっと多くの社員に、ワークスタイリングを積極的に使ってほしいと思っています。日本橋のワークスタイリングに営業所が移ることで、オープンスペースや1人用個室の利用も増えるはずです。百聞は一見にしかずといいますが、一度使ってみれば、その良さが実感できると思うんですよ。あえてワークスタイリングで社内のミーティングを開いてみたり、利用体験会のような機会をつくってみたりしても面白いかもしれませんね。