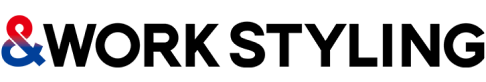導入事例
140部門・月500人が利用 ワークスタイリングは“柔軟な働き方”を支える重要なピース イベント「縁結び」でつながりも醸成
- 5000名以上
- 情報サービス業・インターネット附随サービス業
- 従量課金プラン(SHARE)
- 働き方改革
- ハイブリッドワーク
- 高セキュリティ環境
- すき間時間の有効活用
- 出張・外出先利用
- 充実した設備・心地よい空間
- 企業間交流

杉野未有様(左)と伏⾒梓様(右)
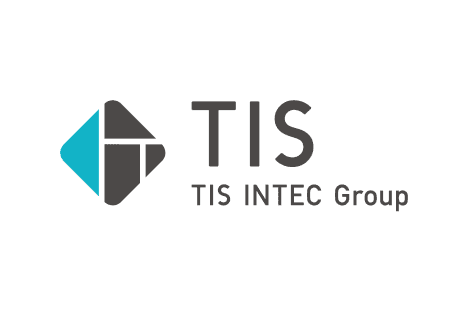
企業名
業種
総合 IT サービス
従業員数
約6千名
設立年
2008年4⽉
導入サービス
従量課⾦プラン(SHARE) 2019年4⽉〜
取材対象者
総務部 杉野未有様/伏⾒梓様
企業紹介
TIS 株式会社様は、ビジネスを⽀える基幹システムやアプリケーションなどを幅広い業界・分野で提供する総合 IT サービス企業です。社員⼀⼈ひとりがパフォーマンスを最⼤限に発揮できる場所を選べるよう、さまざまな取り組みを先駆的に進めてきました。
その⼀つが、ワークスタイリングの導⼊です。 「オフィスか⾃宅か」という⼆者択⼀ではなく、安⼼して働ける“第3の選択肢”として、全国の拠点が使える「従量課⾦プラン(SHARE)」を導⼊。今では全部⾨の 7 割にあたる約 140 部⾨が登録し、⽉間 500 ⼈ほどの社員が利⽤しています。
⼈とつながる「コミュニケーション」と、⼀⼈で仕事に打ち込む「コンセントレーション」。この両⽴をかなえるワークスタイリングの空間設計は、社員の「⾃⽴」と「⾃律」を重んじる TIS の価値観と重なり合っています。
同社ならではの柔軟な働き⽅やワークスタイリングの活⽤シーンについて、総務部の、杉野未有様、伏⾒梓様にお話を伺いました。
■TIS の働き方や取り組みと導入の背景
重視するのは、社員の「自立」と「自律」
――御社は働き⽅について、どんなことを⼤切にされていますか。
杉野様:社員⼀⼈ひとりの考え⽅や置かれている環境はさまざまですが、それぞれが最⼤限のパフォーマンスを発揮できる環境を整えることを⼤切にしています。
会社として特に尊重しているのが、社員の「⾃⽴」と「⾃律」です。⼀⼈ひとりが⾔われたことをただこなすのではなく、主体的に考え⾏動するからこそ、より良い成果やサービスにつながると考えているからです。
「働く場所」についても、⾃分がパフォーマンスを発揮できる場所は、⾃分⾃⾝が⼀番よく知っているはず。ですから、こちらから出社やリモート勤務といった働き⽅を強要することはありません。社員が個々の事情に応じて働く場所を選択できるよう、オフィスでも⾃宅でも安⼼して働ける環境づくりを意識しています。
――御社がこのような柔軟な⽅針を持つようになったのは、いつ頃からですか。
杉野様:東京オリンピックを控えた 2018 年ごろからです。⼤会期間中は多くの⼈が⽇本を訪れ、交通機関が混雑することが予想されていました。政府や東京都からテレワークの推進を求められていたこともあり、当社でも柔軟に働ける環境を整えようという意識が少しずつ⾼まっていきました。
ただ、こうした環境整備は総務だけでは完結できません。セキュリティを確保しながらオフィス外でも働ける ICT 環境や制度づくり、柔軟な働き⽅を受け⼊れる⽂化の醸成も必要です。そのため、総務・情報システム・⼈事の3部⾨が議論を重ね、体制を整えていきました。
総務部にとって重要な仕事の⼀つが、社員に「働く場所」の選択肢を届けること。なかには、さまざまな事情で「⾃宅で働けない」という社員もいます。だからこそ、 「オフィスか⾃宅か」という⼆者択⼀ではなく、“第3の選択肢”としてシェアオフィスであるワークスタイリングを導⼊することにしました。

コロナ禍で定着した柔軟な働き方
――御社は 2018 年に総務省の「テレワーク先駆者百選」に選ばれるなど、コロナ以前から先進的な取り組みを進めてこられました。
杉野様:⼈事部⾨が⼿がけた制度で⾔えば、コアタイムなしのフレックス制度を導⼊しました。1⽇の最低労働時間は2時間、午前5時から午後10時の間で⾃由に働けます。評価制度も⾒直しました。成果だけでなく過程も重視することで、オフィス外で働く社員も、対⾯で接する機会が少ない上司にアピールしやすい仕組みになっています。
制度や環境は整備したものの、すぐに定着したわけではありません。⼤きく変わるきっかけになったのは、やはりコロナ禍です。それまでは主に⼦育てや介護を理由にリモートワークをする社員が多かったのですが、コロナ禍で多くの社員が在宅を余儀なくされました。ただ、全社的に準備していたこともあり、⽐較的スムーズに対応できたと思います。現在、社員の出社率は30%ほどです。

■導入による成果・効果
140部門が登録、月間約500人が利用
――ワークスタイリングのどのような点を評価していただいているのでしょうか。
杉野様:セキュリティ⾯はとても重視している点です。当社は幅広い IT サービスを提供しています。機密性の⾼いデータを取り扱うことも多く、セキュリティの確保が⽋かせません。部外者から端末の画⾯が⾒られない場所で働くことがルールとして定められており、不特定多数が出⼊りするカフェでの業務は認められていません。ですから、働く場所の選択肢は原則的にオフィス、⾃宅、そしてワークスタイリングに限られます。
端末で作業する際は、⾃分の後ろを⼈が通れるような場所は避けるよう推奨しています。
その点、ワークスタイリングは壁を背にした席が意識的に設けられており、とても助かっています。また、スタッフが常駐して⼊退室管理を徹底しているほか、オフィス全体に⽬が⾏き届いている印象があります。
他社のシェアオフィスと⽐べても、ワークスタイリングはセキュリティの意識が⾮常に⾼く、当社の考え⽅に⾮常にフィットしていると感じています。
――全国の拠点が利⽤可能な「従量課⾦プラン(SHARE)」をご契約いただいています。実際の利⽤状況についてお聞かせください。
杉野様:当社には190ほどの部⾨がありますが、そのうち約140部⾨がワークスタイリングに登録しています。利⽤者数は着実に伸びており、直近では⽉間で約500⼈が利⽤しています。⽉に複数回利⽤する社員も珍しくありません。ワークスタイリングは、今では当社の柔軟な働き⽅を⽀える重要なピースになっています。
業務内容や⼈数、働き⽅は部⾨によってさまざまです。例えば、クレジットカードのシステムを担当する部⾨もあれば、特定の企業の勤怠管理や会計のシステムを担当する部⾨もあります。そのため、ワークスタイリングの使い⽅については予算管理も含めて部⾨の裁量に委ねています。

■活用シーン
移動の合間の“つなぎの場”として活用
――どのようなシーンで特に利⽤されているのでしょうか。
杉野様:特に多いのは、営業の社員が都内のワークスタイリングを利⽤するケースです。営業先から次の訪問先へ移動するまでの「つなぎの場」として活⽤しています。営業は1⽇に複数件回るのが通常なので、主要駅の近くにあり移動の合間に使えるワークスタイリングは、とてもありがたい存在のようです。
また、出先から社内のウェブ会議に出席する機会も増えているため、個室のブースもかなり利⽤されています。従量課⾦プラン(SHARE)で個室のみのワークスタイリング拠点を使える点も⼤きいですね。
――総務部のみなさんもワークスタイリングを利⽤されていますか?
杉野様:移動の合間に、私たちもよく利⽤しています。個⼈的には、拠点ごとにデザインが違うところが気に⼊っていて、ピアノが置いてある拠点などもあって、各拠点の個性を感じられます。外出中にどちらの拠点にも⾏ける状況であれば、そのときの気分や好みに応じて「今⽇はこっちに」と選べる楽しさがあります。
伏⾒様:チームで移動することも多いので、訪問先からの帰りにワークスタイリングに⽴ち寄り、メンバー同⼠で振り返りを⾏うこともありますね。

杉野様:私たちはワークスタイリングのデザインに親和性を感じています。ですから、2021年にオープンした豊洲オフィス(東京都江東区)は、ワークスタイリングを⼿がけたデザイン会社と⼀緒につくりました。
――どのようなところに親和性を感じていただけたのでしょうか?
杉野様:⼀番は、コミュニケーションとコンセントレーション(集中)が両⽴できる点です。仲間と集まりたいときもあれば、集中して作業したいときもありますよね。ワークスタイリングには、オープンなスペースや会議室がある⼀⽅で、一人で作業ができるブースも⽤意されており、業務内容や場⾯に応じて最適な場所を⾃律的に選ぶことができます。
こうした考え⽅は、ABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)を重視する当社の価値観としっかり重なっています。豊洲オフィスの各フロアには、ミーティング席や多⽬的に使えるコラボレーションエリアを設けた⼀⽅で、会話・⾷事禁⽌のフォーカスエリアや1 on 1ブースも配置。時と場合に応じて働く場を変えられるように⼯夫しています。
■今後の展望
多様なつながりを生む“縁結び”
――御社は社員の柔軟な働き⽅を尊重しながら、社員同⼠が多様なつながりを持つことも⼤切にされていますね。
伏⾒様:オフィスというハード⾯で良い環境を提供するだけでなく、社員同⼠がつながる「場」をつくるというソフト⾯の取り組みにも⼒を⼊れています。
ワークスタイリングでつながった三井不動産さんと連携しながら、「縁結び」というイベントを企画。2024 年から不定期で開催しています。希望する社員が勤務後にオフィスに集まり、⾷事をしながらゲームやクイズで交流するイベントで、これまでに延べ 400 ⼈近い社員が参加しました。
リモートワークが浸透し、柔軟な働き⽅が可能になった⼀⽅で、どうしても社員同⼠が対⾯でやりとりする機会は減っています。実際、2023 年に実施した社内アンケートでも「コミュニケーションに関する課題感が⾼い」という声が多く寄せられました。
私たち総務部としても、社員がオフィスで顔を合わせ、コミュニケーションを取ることは⼤切だと考えています。ただ、 「明⽇は全員出社しましょう」と呼びかけても、当社の⽂化にはそぐわず 、ポジティブに伝わりません。だからこそ、出社したくなる“きっかけ”をつくることが⼤切だと考え、「縁結び」を始めました。
社員同⼠が年代や部署を超えてつながることは、社員のエンゲージメントを⾼め、結果として組織の成⻑にもつながるはずです。

――社員のみなさんが⾃ら働き⽅をデザインするという御社の価値観は、「すべてのワーカーに『幸せ』な働き⽅を。」というワークスタイリングのパーパスと重なり合っているように感じます。
伏⾒様:ワークスタイリングは、利⽤者同⼠が企業の枠を越えて交流できるイベントやワークショップを頻繁に開いていますよね。当社にも、こうしたイベントに積極的に参加している社員がいます。
私たちの「縁結び」も、回数を重ねるごとに社内で⼝コミが広がり、参加を楽しみにしてくれる社員が増えているのを感じます。社内の要望を受け、東京だけでなく名古屋や⼤阪のオフィスでも開催することができました。これからも、社員が働く時間や場所を⾃ら選びつつ、⼈との“つながり”を持てる。そんな環境を整えていきたいと考えています。